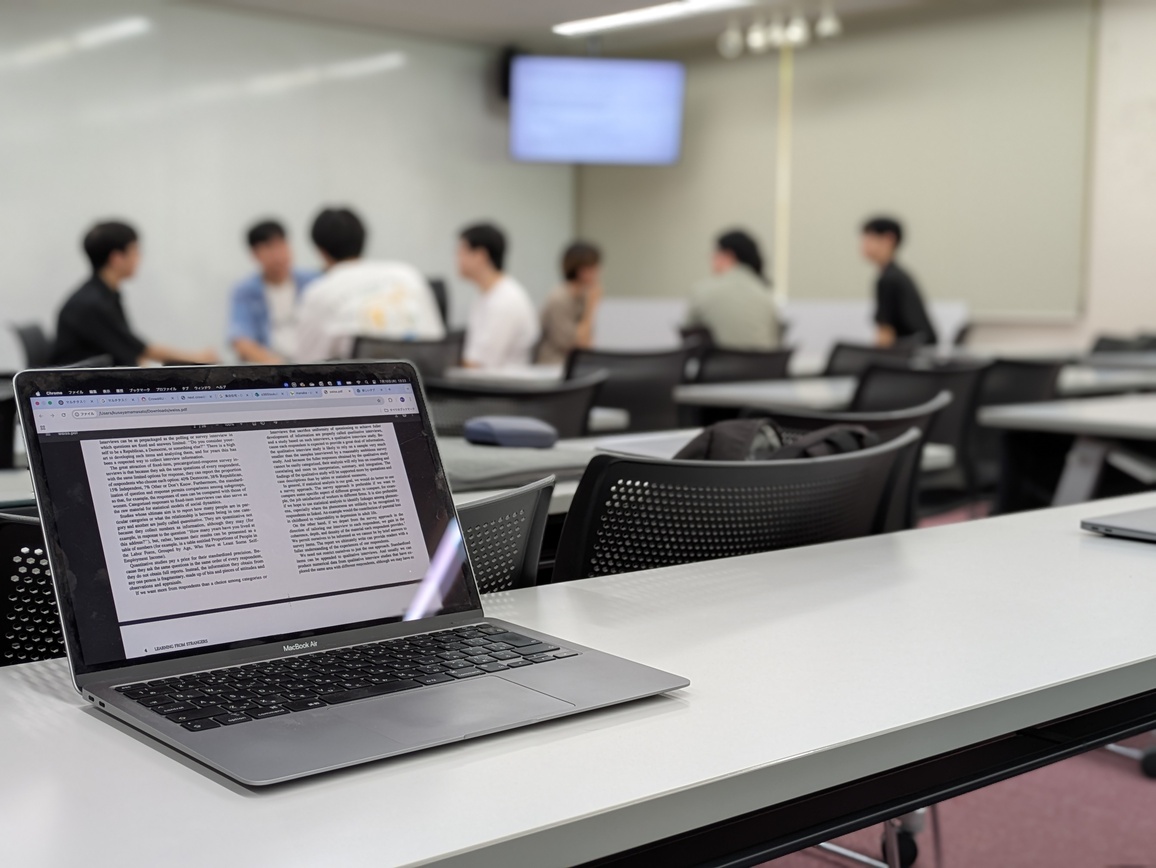小泉 奈央さん
所属: 東京消防庁 四谷消防署 総務課管理係
修了学位プログラム(または専攻): 人間総合科学研究科 体育科学専攻
取得博士号:博士(体育科学)
修了年度:2023年3月満期修了退学、2024年5月学位取得
2009年に順天堂大学を卒業後、東京消防庁に入庁し現在まで勤務。2016年に筑波大学大学院 体育学専攻(博士前期課程)に入学し、2018年に修了。さらに体育科学専攻(博士後期課程)へ進学し、社会人のための長期履修制度を活用しながら、勤務と研究を両立。2018年に第1子、2020年に第2子、2023年に第3子を出産し、子育てをしながら学びを続ける。
――企業のどのような制度を利用して入学されたのでしょうか?
博士前期課程:東京消防庁大学等委託研修を活用して入学。
博士後期課程:自費通学にて進学。在籍中に産休・育休を取得。
東京消防庁は研修制度もとても充実しています。庁内研修も様々あるのですが、外部教育機関への委託研修で職務に必要な専門知識と技術を身につけ、それらを消防行政に活かすことを目的とした庁外研修も多くあります。一例として、大学医学部附属病院での委託研修や、海外の消防事情を調査する研修、大学への委託研修などがあり、私はその中の大学等委託研修を活用して筑波大学大学院博士前期課程に入学しました。博士後期課程は、東京消防庁の委託研修修了後に自費通学として通常の勤務を行いながら修学しました。
こうした修士号や博士号の取得を支援してくれる制度をもつ企業や自治体は他にもあると思います。今後のキャリアを考える上で、そうした制度を活用してみるのも一つの方法だと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
――消防の現場で経験された中で、「研究につなげたい」と思うほど強く課題を感じた出来事は何だったのでしょうか? 博士論文に取り組むテーマとして「食環境」を選ばれた理由を教えてください。
私は東京消防庁で大規模災害発生時の物資調達を担当していました。御嶽山噴火災害では粉じんが多くマスクを外せず、長時間水を飲まずに登山を含む活動を続け、やっと戻ってきて小さなコップ一杯の水を口にする、そんな過酷な状況がありました。東日本大震災では、被災地に派遣された隊員にすぐに食糧を届けられず、東京自体も被災していたため調達が難しい場面もありました。
大規模災害時消防隊の任務は予測困難な状況下で長時間続きますが、食環境は整っていないのが現実です。発災直後は食糧が足りていなかったという調査結果もあり、被災地派遣から体調を崩して帰ってくる隊員も見られました。それでも翌日にはまた24時間勤務が待っている。こうした厳しい現場を目の当たりにし、「大規模災害時には食糧が大きな課題になる」と痛感しました。
だからこそ、この課題を解決するには、公的な財源を動かせるだけの科学的根拠を示す必要があると考えました。その思いが大学院進学につながり、最終的には博士論文にまで取り組むことができました。
――今回の博士論文の成果は、現場の消防活動にどのように役立つと考えていますか? また、今後どのように活用していきたいですか?
博士論文では、大規模災害対応活動における消防隊員の総エネルギー消費量を、実際の活動データに基づいて初めて推定しました。さらに、活動種別ごとの時間あたりエネルギー消費量の標準推定値を算出したことで、各消防本部が被害規模や活動想定に応じて隊員の総エネルギー消費量を推定できるようになりました。こうしたデータは、隊員の準備や活動計画、特に食事や物資の適切な準備に役立ちます。例えば「1日あたりの総エネルギー消費量は4,911kcal(おおよそ5,000kcal)」という根拠を示すことで、消防本部など災害に対応する現場での具体的な食糧計画にも応用できます。 また、社会人として研究に取り組んだことで、自分の働く業界を俯瞰し、客観的に課題を見直す機会を得られました。今後はこの学位を活かし、消防職員がより安全に活動できる環境づくりに貢献していきたいと考えています。
――研究を始めたきっかけや、最初に抱いていた思いを教えてください。仕事と研究を両立する中で、特に大変だったことは何ですか?
私が研究を始めた当初の思いは、簡単に言うと「食事が足りない現場の隊員に、元気に活動できる、体調不良を起こさずに帰って来られる食事を届けたい。そのための根拠となるデータが欲しい」という、非常に漠然としたものでした。それを学術的・科学的な研究に落とし込む方法を考えるのが、本当に大変でした。
さらに、仕事を続けながらの研究だったので、業務と両立するために制度を活用しながらでしたが、日々の業務もあるため大変でした。加えて、出産も挟んだため、研究に最も力を入れたい時期に様々な状況が重なり、試練の連続だったように思います。最近は男性も育児に積極的に関わる方も多くいると思うので、同じような状況の方にも関係する話かと思います。 私は「両方頑張れるかな」と思いながら取り組みましたが、生まれたばかりの新生児は2時間おきに授乳が必要で、赤ちゃんのお世話や授乳の合間に論文の作成を続けたことで本当に体を壊しそうになったこともありました。子育てと論文執筆とのバランスを自分なりに決めて取り組む必要性を感じました。
――来年博士前期課程を修了とともに就職し、育児、仕事、研究の三つを同時進行させながら博士後期課程(社会人)に進みたいという院生もいます。育児をしながらという進学が確定していますが、具体的にどれくらいの準備が必要でしょうか?
社会人1年目は仕事の融通もききにくいのではないかと思います。仕事をしながら就学されている大学院生は休学するか迷う方も多いですが、それぞれの環境で周囲にも相談しながら挑戦していってもらえればと思います。私の場合は、一度離れてしまうと「もう戻れないんじゃないか」「育児や仕事で日々忙しいから、論文はもういいか」と思ってしまいそうで、とても不安でした。だから休学せずに、そのまま走り続けました。そのため、長期履修制度を活用し、修業年限を延長し教育課程を履修しました。
出産後は、育休制度の活用などについてもパートナーとよく相談し、まずは体調管理や赤ちゃんのことを第一にしながら、バランスを考えて取り組んでいくことが大切だと思います。
私の場合は指導教員をはじめとする先生方、職場の上司や同僚のご理解もいただきながら、夫や母に支えてもらい、論文を書き進めることができました。論文審査を受けるときは、審査中、筑波大学内にある学内育児スペースを活用させていただくこともありました。親族に頼れない場合もあると思います。研究活動を続けていく上で、実験や発表や審査など、どうしても第三者の手が必要になることもあると思うので、育児のアウトソーシングの仕組みを早めに調べておくのもいいと思います。もしも可能であれば育児が始まる前に、できるだけ論文を仕上げて投稿するなど研究を進めておくのがよいと思います。ただし、論文を早めに投稿しすぎると、最後に全体を組み立てる段階で調整が難しくなることもあります。ですので、投稿のタイミングと仕上げるバランスが重要です。
就職、結婚、出産と新しい環境で多くの変化があると思うのですが、自分の中で何が大切なのかを明確にして優先順位を決めてひとつひとつのことに取り組んでいくことが大切だと思います。
育児や仕事とともに研究をしていると、学位取得への挑戦を辞める理由もタイミングも何度も訪れると思います。時と場合によってはその方がよい時もあるかもしれません。でも、簡単なことでもいいので、自分の中にひとつでも信念をもっていると踏ん張れる確率が高くなると思います。私も何度も諦めそうになりましたが、「こどもに途中で投げ出す姿を見せたくない」という思いが最後の防波堤となったように思います。
育児・家事・仕事と研究の並走はどうしても作業をする時間が限られます。大変なことも多いですが、一方で時間のやりくりが効率的に行えるようになりました。厳しい状況下でも、諦めずに行動することで打開策が見つかることもありますので、ぜひ挑戦していってください!
――在学中にこれをしておくといいというアドバイスをお願いいたします。
最後に、在学中のおすすめについてお話しします。私は博士前期課程2年間でいろいろな経験をさせてもらったのですが、特に海外研修の制度がとても良かったので、皆さんにもぜひおすすめしたいです※。筑波大学ではこうした制度が結構充実していて、中には単位が取れるものもあります。
筑波大学全学生を対象とした海外留学支援事業(はばたけ!筑大生!)や、大学院共通科目の中で「国際研究プロジェクト・国際インターンシップ」などもあります。また、人間総合科学学術院が募集している「武者修行型学修派遣支援」という自分の研究テーマに沿って海外で調査できる制度もあります。
こういう経験をすると、視野も広がり、大学生活もより充実したものになると思いますので、おすすめです。
※博士後期課程でも対象となっているものもありますので、詳細は各ホームページなどをご確認ください。