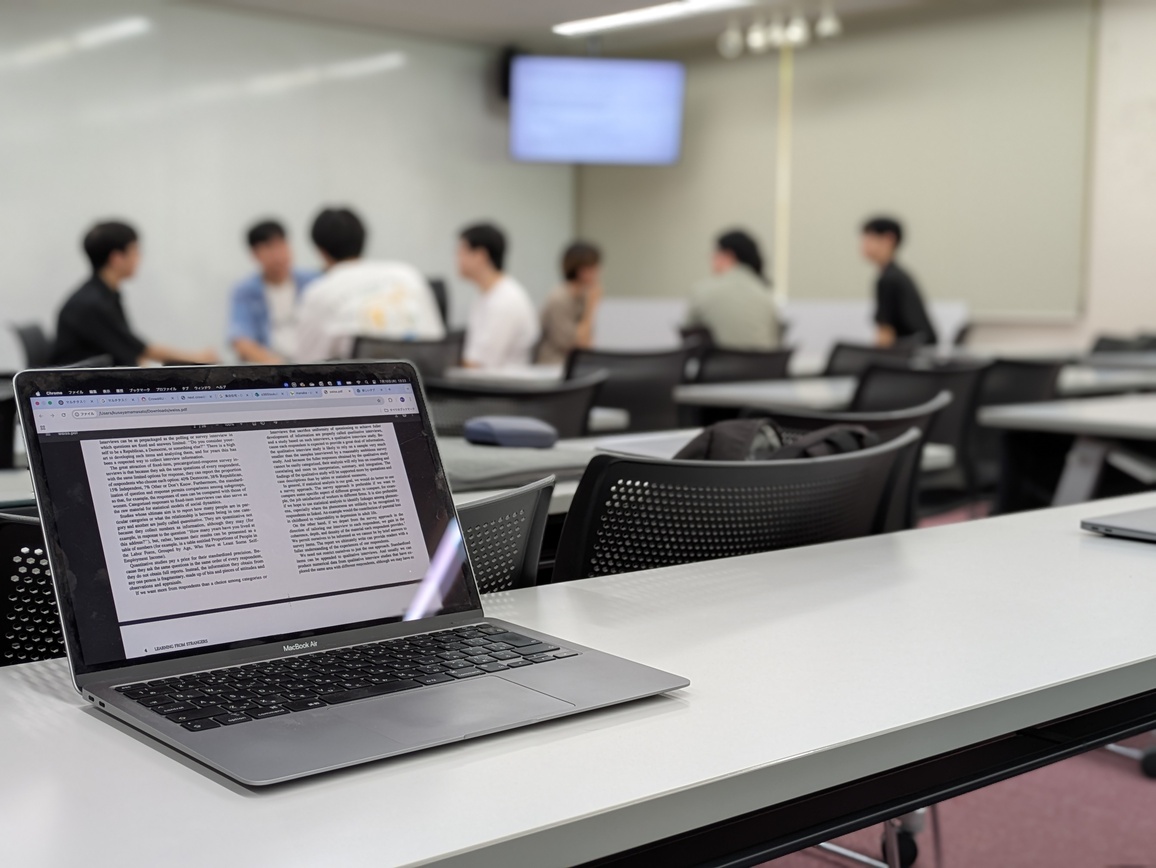坪井 一輝さん
所属:MSD株式会社
修了学位プログラム(または専攻):人間総合科学研究科(一貫制博士課程)生命システム医学専攻
取得博士号:博士(医学)
修了年度:2015年度
――修士課程から博士課程に進んだ理由と大変だったことを教えてください。
修士から博士に進んだのは、「論文の作成に関わりたい」という軽い気持ちからでした。せっかく筑波大学の修士課程に入り、研究に携わる機会を得たのだから、研究者として経験できることは一通り経験したいと思い、修士1年生の頃に博士課程に進むことを決めました。自分で考えた研究テーマに愛着があったことも一因だと思います。
しかし、4年間の博士課程を経験した結果、自分は研究者に向いていないということが身にしみて分かりました。誰かの研究を理解することはできても、オリジナルの発想を生み出したり、未知の領域を切り拓いたりすることが自分には向いていないと感じました。それでも、博士課程での日々は新しい経験ができ、多くのことを学べた良い期間だったと思っています。
研究面での苦労は、毎日実験用マウスや細胞の世話をしなければならなかったことです。特に就活の時期には説明会や面接などで都内との往復が頻繁でしたので、両立が難しかったと感じています。研究以外では、国際交流に力を入れていました。博士課程を終えてから後悔しているのは、もっと様々な経験を積んでおくべきだったということです。実際に履歴書を書いてみた時、資格欄や自己PR欄が真っ白で、恥ずかしい思いをしました。
――博士号が現在の仕事にどう活かされていますか?
博士号の取得は、現在の仕事に大いに役立っています。私がこれまでについた職種はMR(医薬情報担当者)、MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)、OSA(オンコロジー・サイエンティフィック・アフェアーズ)、CS(クリニカル・サイエンティスト)ですが、MSL・OSA・CSといった職種は専門性が高く、医学や理化学、薬学系の修士・博士号を持つ人が多く活躍しています。企業によっては、博士号がなければ就くことができない場合もあります。
私が社内でこれらの職種に異動させてもらえた一つの要因は、間違いなく博士号を持っていたからだと考えています。新卒募集がなかったり、入社するまで知らなかった魅力的な職種はこれまでに経験した以外にも数々ありますが、その中のいくつかは博士号を持っていたことで門戸が開かれました。また、博士課程の研究や経験を話すことで、未経験の職種であっても通用する専門性を有していると評価してもらえる場面も多く、現在までのキャリア形成に非常に有用だったと考えています。
具体的に役立っているスキルとしては、まずプレゼンテーション力や議論のスキルなどコミュニケーション能力が挙げられます。多忙な方々と話す際には、必要な情報をいかに簡潔に伝えるかが重要です。
また、メンタルの強さも欠かせません。専門性が高く、かつ影響力の大きな社内外の方々と話す機会が多いため、相手の意見や雰囲気に流されずに自分の意見を言える強さ、そして自分の不勉強さを受け入れて切り替える強さが必要になります。
さらに、論文を読み続ける習慣や英語力の向上など、日々の学習も重要です。専門性の高い仕事には、自ら知識をアップデートしていく姿勢が不可欠です。言われたことを調べるだけでは、AIと変わりません。加えて、ルールや規制の厳格化に対応できる倫理観も求められています。
私の経験してきた職種では、海外出張やアメリカ本社の社員と海外の先生方との会議に参加することもありました。国内外で疾患の概念や治療方針が異なる場合、博士号取得で得たスキルを活用して、高度な専門性を発揮することが求められます。
――学生時代の研究と経験で役立ったことを教えてください。
私は学生時代、ひたすら研究に明け暮れていました。マウスの世話や細胞培養、解析、論文作成といった研究室での活動が中心でした。
この経験から得られた最大の収穫は、物事の根本を考える癖がついたことです。論文を読む際に論文の結論だけを見て納得するのではなく、結論に至るまでの検証が本当に正しいのかを考えるのと同様です。この考え方は、今の仕事でも非常に役立っています。
――研究活動と就職活動をどのように両立させたのでしょうか?
研究と就職活動の両立で特に意識していたのは、自己管理です。当時の教授は就職活動をあまり応援してくれないタイプだったので、頼れるのは自分だけでした。そこで、まずは就職活動の状況をこまめにメモに残すようにしました。「何社受けているか、会社の特徴、各社の担当者、各社の選考状況、面接等のやり取り」などを記録し、省みて必要な行動を洗い出し、研究と就職活動の予定に反映し、期限を決めて行動していました。
正直なところ、最初のうちは管理がいい加減でした。しかし、途中でその重要性に気づいてからは、就職支援課の利用やセミナー参加の時間も確保できるようになり、両立がスムーズになりました。
漠然と過ごしていると、甘えから無駄な時間が生まれ、研究を理由にして新しい行動をとることを避けてしまいがちでした。そのため、私は、自分で自分を管理することを意識していました。
――英語の読み書きの力が必要になる中で、どのようにしてその力を高められたのでしょうか?
正直に申し上げると、私はTOEICやTOEFLといった資格試験をほとんど受けていません。その代わりに、自分をあえて英語を使わざるを得ない環境に置くことで、実践的に英語力を鍛えてきました。例えば在学中は留学プログラムに積極的に参加し、日常的に英語で話しかけられる状況に身を置くことで、なんとか対応できるようになっていきました。また、研究活動を通じて論文を読み続ける中で、最初は理解できなくても、次第に内容をつかめるようになりました。
就職後も、海外出張の機会があれば、経験が少なくても積極的に手を挙げるようにしています。
ただし、もし転職を考えるのであれば、資格がないことで「目に見える実績」が不足し、評価されにくい可能性があります。そのため、キャリアを築く上では、TOEICなどの資格や具体的な実績を確保しておくことも重要だと感じています。