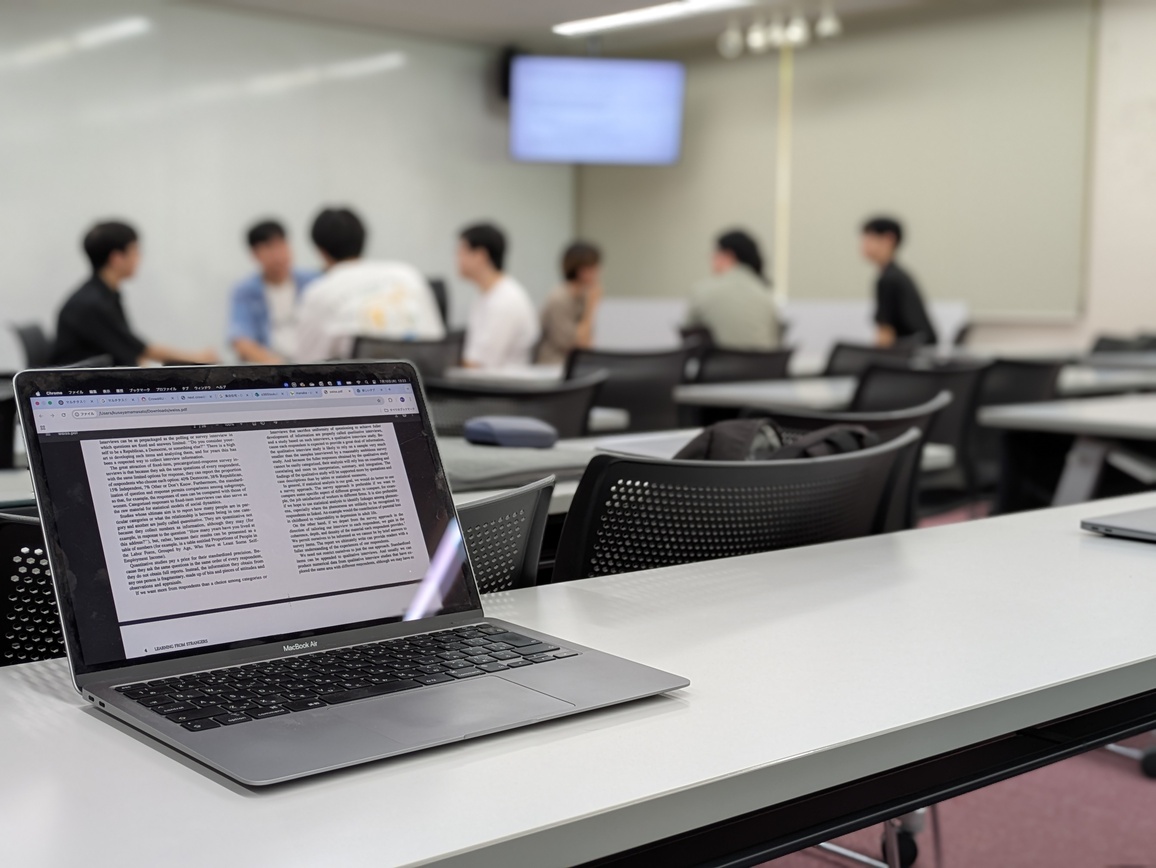長谷川 大悟さん
所属:メディリハプラス株式会社 代表取締役
修了学位プログラム:人間総合科学研究科(3年制博士課程)ヒューマン・ケア科学専攻
取得学位:博士(ヒューマン・ケア科学)
修了年度:2017年度
中学生からの夢であった理学療法士免許を取得後、茨城県内の病院や介護施設などで勤務。「すべての答えは現場にある」を肝に据え、現場課題の解決策を社会実装させるためには、専門的な学びが必要であると感じ、大学院へ進学し2018年3月に修了。別法人に勤めながら、自身でも会社を経営している。筑波大学の非常勤研究員や私立大学の非常勤講師、NPO法人の代表理事、公益社団法人の常務理事などを兼任。医療・介護現場での臨床経験を基盤に行政事業にも参画する。机上議論に終始することなくフィールドワークは欠かさない。
――大学院進学のきっかけと現在の活動について教えてください。
「現場の疑問から研究、そして社会実装へ」
臨床に携わる中で生じた数々の疑問を「分からない」で終わらせるのか、それとも「解明すべき問い」として挑むのか。この選択が私を博士課程へと導きました。専門領域で本格的に取り組むには、研究手法や論文作成の基礎を体系的に学ぶ必要があると感じ、社会人学生として仕事と学業の両立を覚悟し、博士課程に進学しました。
現在は、法人職員としての業務にとどまらず、会社経営、大学での教育・研究、NPOを通じた社会貢献、企業との企画展開や行政事業、講演活動など幅広く従事しています。理学療法士としての専門性を基盤に、臨床・教育・研究・経営・各種活動を有機的に結び付け、その成果を社会へ実装することを使命としています。
――博士課程で得られた「学位」よりも「経験」に価値があるとおっしゃっていますが、具体的にどのような経験がご自身にとって最も大きな糧になったと感じますか?
「博士課程の最大の成果は”学位”ではなく”経験”」
博士号という称号自体に大きな意味はありません。真に価値があるのは、課程を通じて培われた経験であり、それは批判的思考力や課題発見力あるいは課題を解決するために構想し実行する力を養うことにあると考えます。
臨床現場では学位が直接役立つとは限らないものの、多様な人との出会い、議論、試行錯誤を通じて得た知見は、仕事や社会活動を推進する上で欠かせない能力であり、今の行動の礎となっています。
失敗も成功も重ねたからこそ培われた胆力は、どのような状況にあっても臆することなく動じない心構えを生み、それこそが博士課程で得た最大の武器であると確信しています。
――どのように「行動する」モチベーションを保っているのでしょうか?
「自信は行動から生まれる」
「行動が知性を磨き、出会いが未来を拓く」。この信念を肝に据え、誰よりも人と会い、催事に参加し、人から学ぶことを意識してきました。現在の活動もまさにその延長線上にあります。
制度の矛盾や社会課題に対して嘆くだけでは何も変わりません。「行動しなければ現状を黙認していることと同じである」という確信が、自分を行動へと駆り立てています。課題に直面したとしても、批判に終始するのではなく、常識を疑い、慣例に捉われず、議論の場に参画すること。その行動の先にこそ、社会変革の契機があるはずです。
行動を通じて得られる出会いと経験が自信を育みます。よき出会いを求めてぜひ行動してみてください。
――博士課程での経験を通じて、どのような場面で「コミュニケーション力が磨かれた」と実感されましたか?
「ゼロを一に変える行動が対話力を育む」
在学中は分野外の講義や学会、様々な催事に積極的に参加しました。成果が見込めるか否かに関わらず、挑戦を重ねたことが、結果としてコミュニケーション能力を高めるきっかけにつながると思います。
多くの発表を聞き、研究者に問いを投げかけ、他分野の方々と議論することで知識は更新され、自然と対話力も鍛えられていったように思います。「行動しなければゼロのまま」。一歩踏み出すことで必ず出会いと学びがあるという姿勢で臨んだ経験が、その後の活動基盤を形成していくのだと思います。そこで得られる経験は、インターネットでは決して見つからない財産になっています。
――博士人材に求める資質とはどのようなものだとお考えですか?
「優れるな、異なれ」
これまで学業や仕事においては知識量が求められてきましたが、知識量で勝負する時代は終わりを告げています。知識処理はAIに代替され、これからは人間的な魅力すなわち好奇心や創造力といった非認知能力こそが価値を生みます。創造的な視座を持ち、新たな価値を発見するためには、何よりも行動が必要です。
AIが普及する時代にあっては、異なる柔軟な発想や人との協働を支えるコミュニケーション力が不可欠であると考えます。行動を通じて価値観が変わったのであれば、自分の専門領域において質にこだわり、未知なる課題を探し出し、自分にできることは何かという大義を持って挑戦してほしいと思います。
筑波大学には、学際的な協働・共創によって従来の学問では解決できない課題に挑戦できる土壌があります。分野を越えて横断的に学修し、新しい価値を見出す姿勢こそ、これからの博士人材に求められるものかと思います。
――博士課程に進む上で、「最短修了を目指す」ことと「経験を重ねる」ことの間で迷う学生も多いと思います。長谷川さんご自身は、どのような考えでそのバランスを取られてきましたか?
「博士号は肩書きではなく、挑戦の副産物」
最短修了を目指すか、幅広い経験を重ねるか。その選択に正解はありません。大切なことは「何のために大学院に進学したのか」という原点を見失わないことです。
学位取得そのものを目的とするなら、計画的に最短で修了を目指せばよいでしょう。一方、学位よりも経験の蓄積を目的とするなら、修了時期にこだわる必要はありません。知識を深めるだけなら、今や世界中の情報は容易に得られるため、大学院での学びは不要なのかもしれません。結局のところ、「何を目的として大学院に来たのか」という原点に立ち返ることが重要であり、大学院での学びの本質は、挑戦の過程そのものにあると考えます。
私自身もなお挑戦の途上にあります。単に一つの取り組みに満足せず、批判や迷いに捉われるのではなく、原点を腰に据え、行動によって未来を切り拓いていきたいと思います。