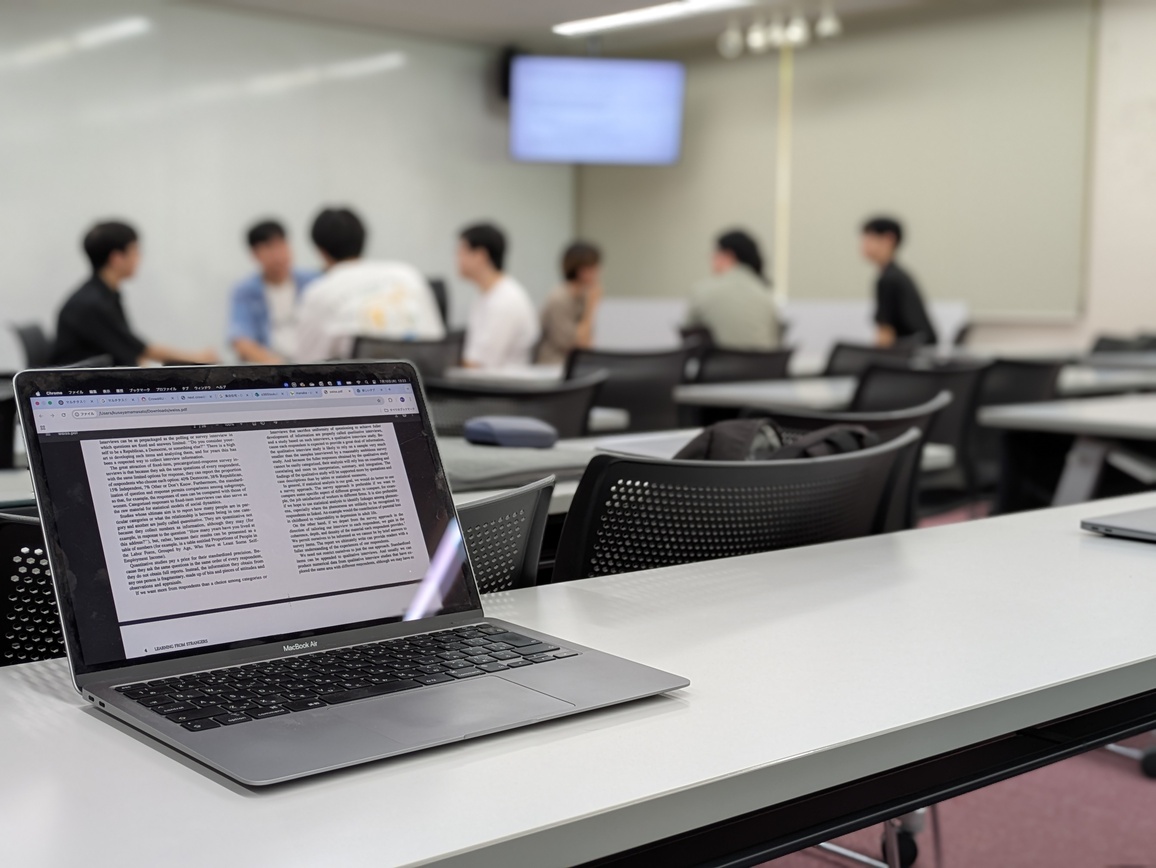稲福 和史さん
所属:株式会社リクルート
修了学位プログラム(または専攻):人間総合科学学術院人間総合科学研究群(博士後期課程)情報学学位プログラム
取得博士号:博士(情報学)
修了年度: 2022年度
2014年筑波大学情報学群知識情報・図書館学類に入学。2018年、同図書館情報メディア研究科 図書館情報メディア専攻(博士前期課程)へ進学。2020年、同人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 情報学学位プログラム(博士後期課程)へ進学し、2022年に修了。また、2020年の博士後期課程進学と同時に、株式会社リクルートへデータサイエンティストとして入社し、現在まで勤務。2023年からはアナリティクスエンジニアとしてデータマネジメントの業務に従事。
――在学中の学びと現在のキャリアはつながっていますか?
私の場合、在学中の研究テーマと現在の仕事が直接つながっているわけではありません。
「なぜ研究テーマと仕事が直結しなかったのか?」という点についてですが、これはシンプルに言うと就職活動の時に研究テーマを軸にしなかったからです。
私は就職を考えたとき、「いろいろなサービスのデータ分析に携わりながら生きていけるなら十分だ」と受け止めていました。ですので、「研究テーマをそのまま仕事にしなくてもいい」というスタンスでした。
もちろん、同じ情報学学位プログラム出身でも、研究と業務をしっかり結びつけている方もいらっしゃいます。例えば、自然言語処理(NLP)や予測モデルを専門にして、ITの分野で大学院での研究をそのまま応用して働いている方もいます。
――研究で培ったスキルの中で、特に仕事で役立ったものは何でしょうか?
研究を通じて身につけたスキルは大いに役立ちました。
ハードスキルとしては、プログラミング、データベース、統計といった技術。ソフトスキルとしては、文献調査(サーベイ)やプレゼンテーション能力などです。これらはいずれも業務の中でそのまま活かすことができました。
私は新卒でデータサイエンティストとして入社しましたが、その時期には特にハードスキルが役立ちました。授業や研究で扱った手法を「これは知っている」とスムーズに実装できたことで、早い段階から成果を出せたのではないかと考えています。
その後、アナリティクスエンジニアに異動してからは、スキルそのものよりも「モチベーション」の面で研究経験が活きてきたと感じています。データサイエンティスト時代には「もっときれいなデータがあれば、課題解決に集中できるのに」と思っていましたが、異動後はその環境を整える立場となり、課題に前向きに取り組むことができました。この姿勢は、研究室で培った経験や学びの影響が大きいのではないかと感じています。結論として、大学での学びは実務に非常に直結しているという実感があります。
――博士課程に進もうと決めたとき、どのようなことを意識されていましたか?
キャリアを考える上で、私が大切にしてきたのは「できるだけ選択肢を広げること」です。博士課程に進んだときも、将来のキャリアパスを狭めず、選べる道を増やしていきたいと考えていました。現在も現職にとどまっているのは、さらなるスキルアップを通じて、より多くの仕事を選べるようになりたいからです。
また、社会人博士も新卒博士も珍しい存在ではなくなってきています。修士を終えてすぐ就職する人もいれば、働きながら博士課程に進む人もいます。そのように多様なキャリアの形がある中で、博士号の取得や研究に対しても、もっと気軽にチャレンジして良いのではないかと考えています。
――修士課程での研究経験は、アナリティクスエンジニアの仕事とどのように重なる部分があるのでしょうか?
アナリティクスエンジニアは、データを整備する役割を担いますが、データを活用するデータサイエンティストとの境界は曖昧です。必要に応じて両方の役割を果たす柔軟な姿勢が大切だと思います。博士課程や修士課程での研究でも、データの収集・加工・分析から論文執筆まで、一連の流れを自分で担うことが多いため、この点には大きな共通性や相乗効果があると感じています。
もう一つ共通点があるとすれば「泥臭い作業に几帳面に取り組めること」でしょうか。「データサイエンスの仕事の9割は前処理」と言われますが、実際にその工程を効率化し、品質を高めていくのがアナリティクスエンジニアの重要な役割です。ソフトウェア工学の技術を活用しつつ、データの正確性を徹底して検証し、「本当に正しいデータかどうか」を多角的に担保する几帳面さや根性が求められます。
研究活動も同様に、実験設計を丁寧に行い、前処理を地道に積み重ね、分析を経て結果をまとめるという過程が不可欠です。こうした姿勢は、アナリティクスエンジニアをはじめ、データに携わる多くの仕事に共通する資質であると考えています。
――大学院での研究活動は、将来のキャリア形成において、どのような意味を持つのでしょうか?
キャリアパスは多様です。だからこそ「自由に働き、自由に研究してよい」と思っています。その際に大切なのは、自分がその選択で何を得たいのかをしっかり突き詰めて考えることです。私は社会人博士として研究を進めましたが、振り返ると「フルタイムで博士課程に専念してもよかったかな」と思う部分もあります。当時は十分に考え切れておらず、多少の後悔もあります。ただし、社会人博士を選んだからといって不満があるわけではなく、それもまた一つの価値ある経験だったと感じています。
お伝えしたいのは、「研究テーマと仕事が必ずしも直結しなくても、研究で得たマインドや学びは必ず活きる」ということです。例えば、1年生の必修科目「知識情報概論」で学んだ内容が、10年以上経ってから実務に役立つとは思いもしませんでした。人生には思わぬ伏線が張られているものです。地道な実験や研究、論文執筆の経験は確実に力となり、実務に直結して活かせます。そのため、「研究テーマを必ず仕事に直結させなければならない」という発想に縛られる必要はないと考えています。
――フルタイム博士と社会人博士の一番大きな違いは、どのような点だとお考えですか?
フルタイム博士と社会人博士の一番大きな違いは、「自分の研究以外にどれだけ時間を使えるか」だと思います。社会人博士に限らず自分の研究が最優先なのはもちろんですが、どうしてもそれでいっぱいいっぱいになってしまうケースは多いと思います。
フルタイム博士であれば、自分の研究以外にも多くの経験を積むことができます。例えば、TA(ティーチング・アシスタント)やTF(ティーチング・フェロー)として講義に関わることや、学部生・修士ゼミで議論するなど、教育者・研究者としての素養を磨く時間を持つこともできます。さらに、学位論文のための研究以外にも、少し寄り道して違う研究をしてみたり、他分野の論文を読み込む余裕があるのも、フルタイム博士の大きな魅力だと思います。
逆に社会人博士の場合は、限られた時間で研究を進める計画性が身につくと考えます。私は「この論文とこの論文を出せば博士号の要件を満たせる」というように、修了までの最短ルートを計画立てて取り組みました。修士では毎年国内外のカンファレンスに3本程度出していましたが、博士課程での業績は論文誌1本と国際会議2本と少なめです。ただ、修士の業績と合わせて、修了要件はきちんと満たすことができました。振り返れば、趣向を変えた研究や後輩ゼミへの出席などに積極的に割ける時間を作れないことが惜しかったですね。一方、働きながら得られた興味や気づきや研究に活かせるので、新たな角度から見つめられる点では社会人博士もおすすめしたいです。