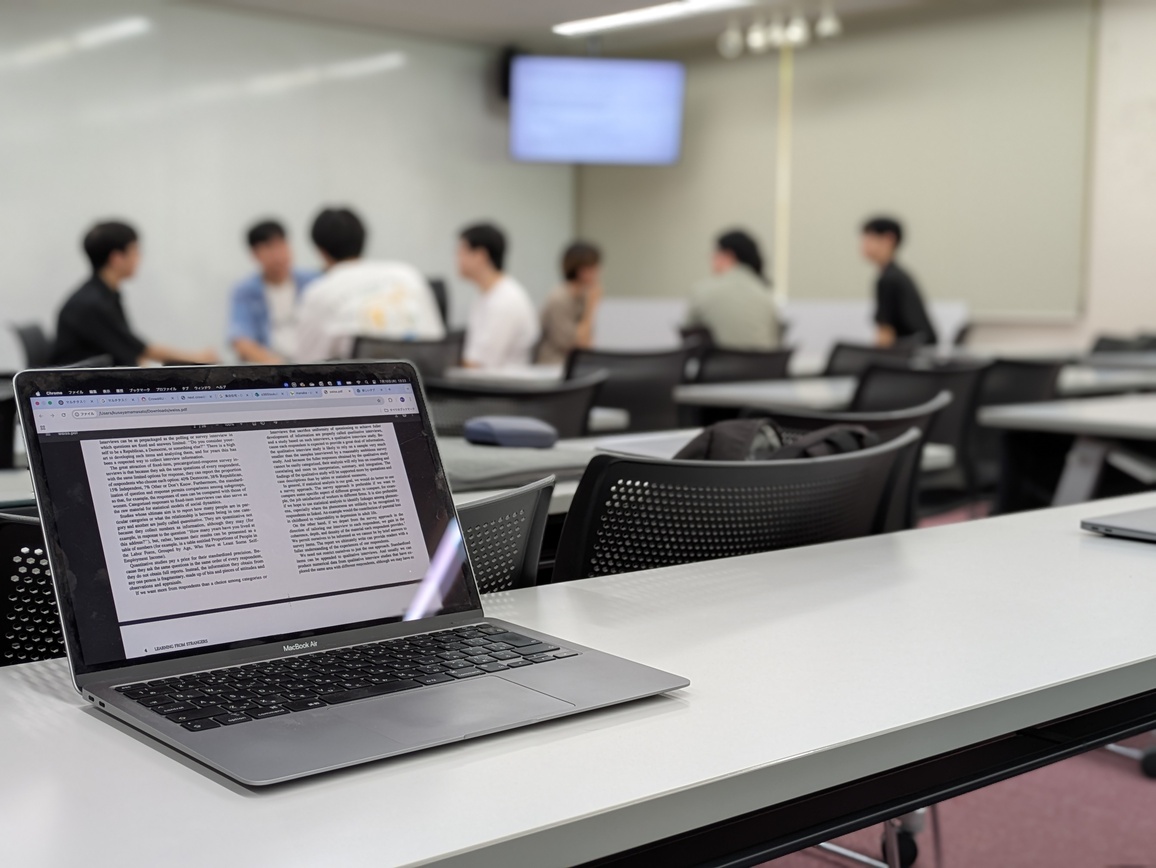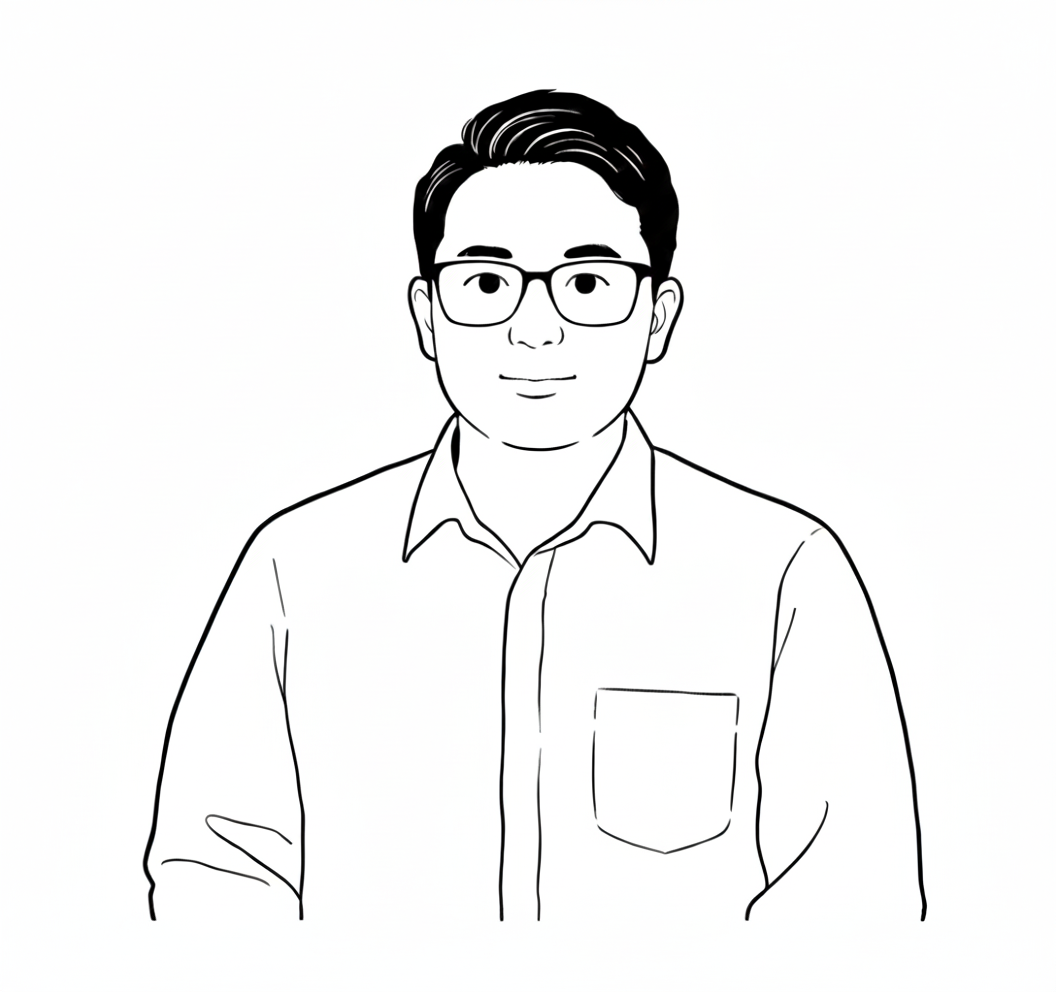
金井 雅仁さん
所属:コンサルティング会社勤務
修了学位プログラム(または専攻):人間総合科学研究科(博士後期課程)心理学専攻
取得博士号:博士(心理学)
修了年度: 2017年度
2013年筑波大学人間学群心理学類卒。2015年人間総合科学研究科 心理専攻(博士前期課程)心理基礎コース修了。その後、博士後期課程に進学し、日本学術振興会特別研究員(DC1)を経て2017年度修了。研究テーマは自己観・身体・感情認識・感情制御の関連。2018年より現職。大手企業へのコンサルティングや学術機関との共同研究等に従事。現在は妻と二人暮らし。趣味は動物園の視察。
――大学院ではどのようなことを学び、それが現在の仕事にどのように役立っていますか?
私は大学院で「人間の感情」をテーマに研究していました。社会心理学や生理心理学の理論、測定手法、分析技法を駆使して、質問紙調査、実験法、生理反応の測定など、さまざまな方法を組み合わせて研究を行っていました。つまり、心理学の中でもかなり基礎研究寄りの分野で学んでいたのです。その後、学位を取得してコンサルティング会社に入社しました。
コンサルティング業界は本当に幅広く、経営戦略に特化したコンサルタントもいれば、ITに特化したコンサルタントもいます。私が所属しているのは、その中でもデータやAIの活用に関する専門部隊です。ここには、機械学習や統計分析、AI技術に加え、データを蓄積・活用するためのシステム設計の専門家が集まっています。私がこの分野を選んだ理由は、何よりも「データ分析が楽しい」と感じたこと、そしてデータ分析に将来性を強く感じたことです。
心理学には理論や測定、分析、実践といったさまざまな側面がありますが、私が最も楽しさを感じたのは「分析」の部分でした。また、日本は今後確実に人口が減り、労働力も不足していくことを考慮すると、限られた人数で効率的に働くためには、データに基づく迅速な意思決定や、AIへの仕事の移行が不可欠です。そう考え、データ分析の可能性に未来を感じたことが、私がこの領域を選んだ大きな理由です。
現在の仕事の軸も「データ」です。私自身のスローガンは「データに基づく意思決定が当たり前の社会を作る」こと。その実現に向けて、企業がデータを有効に活用できるようさまざまな支援をしています。
具体的には、入社初期にはBIアプリケーション(利用者が複雑な分析をしなくてもクリック操作で経営情報を可視化できるツール)を開発したり、その裏側でデータをつなぐ仕組みや蓄積する基盤を整備したりしてきました。ここ数年では、自分自身がデータを活用して業務改善を進める取り組みにも多く携わってきました。
――大学院でのどのような技術や経験が会社に入ってから役立っていますか?
私の場合はとてもシンプルで、「大学院で身につけた分析技術」が一番役立っています。
「大学で培える能力」は何か整理してみてください。その中には、学問分野を問わず育つ、汎用的な力——たとえば、思考力、表現力、読解力、作業をまとめあげる力といったものもあります。一方で、より専門的な研究方法に関するスキルや、専門領域における学術的な知見などもあります。
私はその中でも「研究方法のスキル」、特に統計や測定といった技術が今の仕事に直結しました。それは、私がそうした技術を必要とする職場を選んだからでもあります。よく、大学で身に着ける論理的思考力は役立たないのかという質問を受けることがあるのですが、コンサルティング業界には高い基礎能力を持った人が多く集まるため、私自身にとっての差別化要因は「測定など専門的な技術をしっかり磨いてきたこと」でした。
私がお伝えしたいのは、キャリアを考えるときに“設計”をしっかりしてほしいということです。
私のように培った方法論を武器にする道もあります。研究職ではなくても、医薬品の営業のような形で培った専門知識を活かす仕事もあります。あるいは教育職や対人支援職として、学術的な専門知識を人に伝える形で活かす道もあります。
大切なのは、自分がこれまで身につけた力を「棚卸し」し、自分はどこを武器にしていきたいのかを明確にすることです。そうすればキャリアの方向性は格段に決めやすくなります。
――もともとはアカデミックな道を志していたそうですが、そこから民間の道を選ばれた理由や経緯について教えてください。
もともとは「大学教員として研究も教育も行い、英文論文もどんどん書きながら最前線で活躍したい」と思っていました。しかし、学会で知り合う方たちと自分の能力を比べてみたり、大学を取り巻く環境の変化を知ったりする中で、「そこまでは難しいかな」と感じる時がありました。つまり、最初に描いていた『なりたい自分』と、大学のキャリアを進むことで到達できるゴールが少し違うのではないか、というネガティブな理由がありました。
一方で、ポジティブな理由もたくさんあります。私は幸い、どんな環境でも楽しめるタイプで、難しい問題を解くプロセス自体が楽しいタイプなので、向き合う作業が研究である必要は必ずしもなかったのです。民間企業で、お客様と一緒に問題解決をしていくことも、とても楽しいだろうと感じました。また、民間では十分な給与が得られることや、住む場所を固定しやすいことも魅力でした。こうした「大学はちょっと違うな」という思いと、「民間企業はこんなに良いことや楽しいことがある」という両方の理由で、民間で働く道を選ぶことになりました。このことについては、2年間かけてじっくり考えました。
もちろん、研究自体は面白いです。当時も学会に行く度「研究者は面白いな」と感じていました。しかし、先輩や先生方の姿を見て、「自分はどうするべきだろう」と悩む時期もありました。この2年間の迷いのプロセスがあったからこそ、自信を持って民間での道を選べたと思います。時間はかかりましたが、こうした悩みを経ることは、きっと大切なプロセスだと思います。
だからこそ、そういうことを安心して話せる相手を作ることが重要です。今の私の場合、最近出張が多かったため半分は妻、3割はAIに話を聞いてもらっています。残り2割は大学時代や職場の友人ですが、昔に比べて会える機会は少なくなってしまったため、テクノロジーを駆使して一人で貯め込まないようにしています。自分の気持ちを落ち着けたり、考えを整理したりするためにも、考えを言葉にして出力することはとても大事です。もし話を聞いてくれる人がいるなら、そのような生涯の友を大切にするとよいと思います。
――研究以外の分野に飛び込むことに不安を感じる学生も多いと思いますが、その点についてアドバイスをいただけますか? 大学院で学んだ専門分野以外にも挑戦することについて、どう思われますか?
私は皆さんに「専門を変えたり広げたりすることの楽しさ」を知ってほしいと思っています。私は心理学という分野から、あえて心理学以外の領域に飛び込みました。大変なこともありましたが、本当に多くを学ぶことができました。
具体的には、機械学習やAI、自然言語処理、BIアプリ・システム構築、データベースの仕組みなど。さらには、通信やマーケティングなどのビジネス領域にも詳しくなりました。管理職になってからは、チームマネジメントや若手教育にも携わっています。データを扱う以上、法律の知識も自然と必要になり、そうした学びも得られています。
つまり、専門を広げることで新しい知識やスキルを吸収し続けることは、とても楽しいということです。専門性を軸にしながら、それを広げて次のステップにつなげることを意識してみてほしい。そうすれば、キャリアの先にもっと楽しい未来が待っていると思います。
――大学院生がこれからキャリアを築いていくうえで、身につけておくべき力は何だと思われますか?
博士課程の本人が武器として定義する能力が、そのまま求められる能力になるケースが多いと思います。ジェネラルな能力で勝負する人は、それを磨けばいいですし、専門性で勝負する人は、その専門を深めればいいのです。ただ、それだけだとメッセージとして単純すぎると思います。そこで私が強調したいのは、「目指すキャリアを踏まえて伸ばすべき力を設計する力」です。
自分の境遇や専攻、研究室で得られる能力を整理して、「どこを武器にしたいか」を一度仮決めしてみてください。大事なのは「仮」でいいということです。人生を歩む中で考えは必ず変わりますから。一本に絞らず、仮に決めた武器とその周辺領域を伸ばしていく。人によっては知識かもしれないし、方法論やコミュニケーション力かもしれません。その設計をしておくこと、その力が大学院生に今求められている力だと思います。